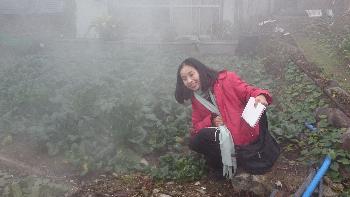『ふるさとの食の宝を守り継いでいくこと』
食・農ネットワーク運営委員 持田成子
豊かな自然と美味しい水、食材に恵まれた熊本に生まれ育ち、野菜ソムリエの資格に出逢って16年。県内各地を旬の農産物を求めて歩き回る中で、故郷の食の豊かさをより深く感じるようになりました。
どの地域にもその風土や産物の中から先人たちによって、生活の知恵を生かして作られてきた歴史と伝統をもった郷土料理が存在し、独特の食文化が育まれています。訪ね歩く度にその土地の自然の恩恵の上に成り立つ郷土食や保存食にふれる一方で、ライフスタイルや価値観の多様化により農村地域であっても食の姿かたちは変わりふるさとの味が次第に失われてきていることも耳にすることが少なくありません。
地域でとれる新鮮な旬の農産物を生かし、栄養的にもバランスのとれた郷土の味として培った料理や手づくりの加工食品、伝統の技=地元の食材が消えていく…この変化は即ち栽培される農産物の種や品目品種の変化と相通じると思えるようになりました。
日本原産の野菜は少なく、「ミツバ」「ウド」「セリ」等で、古代に伝来した稲をはじめ渡来作物がほとんどなのです。その地域の気候風土の中で栽培と採種・選抜を繰り返されながら、各地の固有条件に適応し、地域に守られ生き続けて、在来種になってきたと思われます。
私たち日本人は、在来種に食を支えてもらいながら命を繋いできたといっても過言ではないのです。農家では種がなくなると貴重な食材がなくなってしまうため、地域で、集落で、個人で、命がけで種を守ってきたと聞き及びます。そして、その在来種を「守り」「食べ」「繋ぐ」ことで、それぞれの地域の特有の風土の中で地域の食文化を育んできたということなのでしょう。…なのに、種は失われつつあり、危機にたたされているところもあるようです。なくなってしまっては取り返しがつかないと切に思います。
熊本大学が中心となり、地域に古くから根ざしてきた作物や有用植物の保全・普及を目的として2016年3月に設立・活動している「くまもと在来種研究会」の一員として、「くまもとふるさと食の名人」としても、豊かな自然に育まれてきたその地域の伝統・文化・風習のなかから生まれてきた「郷土の味」、懐かしい味を先達から学び、そして次世代に受け継いでいくことの大切さを思うこの頃です。